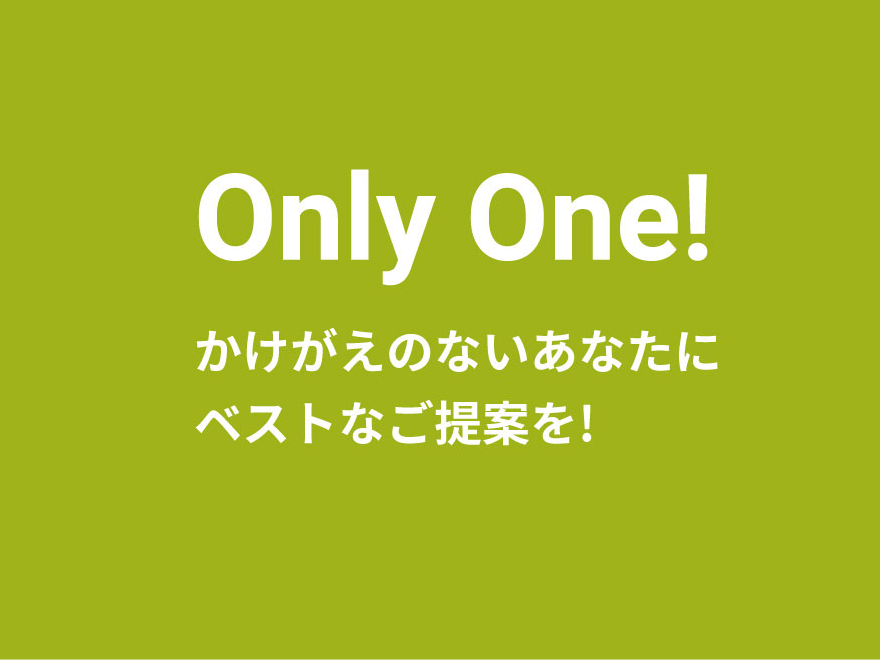龍谷大学
新居理有先生
1982年生まれ。京都大学にて博士(経済学)を取得。2011年から複数の大学での勤務を経て、2023年からは龍谷大学経済学部にて、大学教員として経済学の研究・教育に尽力している。主な分野はマクロ経済学や財政政策。一方で、経済分野の記事を中心にライターとしても活動している。
1.政府の財政運営が持つ役割とは何か?
財政とは、政府(国や地方自治体など)が行う経済活動のことです。政府は幅広い分野で公共サービスを提供しており、私たちの生活を支えています。たとえば、ゴミ収集、学校教育、警察や消防、年金や医療などの社会保障、道路や橋といったインフラの整備など、公共サービスは多岐に渡ります。
なぜ政府はこれらの公共サービスを提供しているのでしょうか?財政の役割は3つあると言われています。
一つめは、民間での取引がうまくいかない場合に政府が介入するというものです。たとえば私たちが自由に通行できる道路は、政府なしで行き渡らせることは難しいでしょう。
自分が負担しなくても、他の人たちが道路を造ってくれれば皆と同じように道路を移動するというサービスを享受できるからです。
このようなサービスには対価が充分に支払われず、民間での取引だけでは、社会で必要とされるほど供給されないことが知られています。このような性質を持つ公共サービスは、政府による供給が必要です。
二つめは、所得の再分配を通じて格差を縮めるはたらきです。どれだけ皆が努力したとしても、所得格差が生じてしまうことがあります。所得格差を縮めるべきだとしても、人々の慈愛精神だけでは所得が低い人たちを支援するのは難しいでしょう。政府の税や社会保障の制度を用いて、半ば強制的に所得を配り直す仕組みが必要です。
最後に、景気の波を落ち着かせ、特に不況の悪影響を和らげるというものです。不況の影響は全国民に及ぶので、民間による保険サービスなどではリスクに対処できないと考えられます。不況の際には公共事業や減税などにより悪影響を和らげ、景気が回復したら景気対策の財源負担をおってもらう。こうした役割を政府が担う必要があります。
まとめると、政府が私たちの生活のために提供している公共サービスは多岐に渡る、また政府は公共サービスを提供すべき理由(おうべき役割)もあるということがわかります。
2.現在の財政運営が抱える課題点について
少子高齢化や家族のあり方の変化が進み、今までは民間でやりくりしていた動きでも、政府が担うべき活動が増えてきています。たとえば、サザエさんのように3世代が一つの家で暮らしているとしましょう。誰か1人が病気・怪我をしても、家族によるケアで乗り越えられるかもしれません。
しかし核家族や単身世帯が増えている今、医療や介護ケアは政府の役割がより大きくなっていると考えるべきでしょう。政府の役割が拡大することで、財政負担はどんどん大きくなっています。社会保障給付の増加を中心として、歳出額は今後とも増え続ける圧力がかかると見込まれます。
上記のような背景を踏まえ、2つの課題を取り上げます。1つめの課題は、財政赤字が出続けており、GDPに対する政府債務残高が大きくなり続けていることです。今後政府が借入に行き詰まってしまったら、公共サービスのために必要となる財源を調達できなくなるおそれがあります。
赤字を小さくし改善するには、税収を大きくするか、政府支出を小さくするかのいずれかの対応が必要です。どのような政策が必要となるか、私自身も研究を進めてきました(Arai, 2011; Arai and Ueda, 2013; Arai and akazawa, 2014)。
しかし、ここで2つめの課題に直面します。財政赤字を止めるための制度・政策の見直しが難しいことです。
たとえば、税収を大きくするための税制改革は、今の日本では強い反発が起こる可能性が高いです。消費税を増税した内閣はもたなかったと言われるほど、今までも強い政治的抵抗がありました。今後の消費増税などの税制改革には、より強い抵抗が生じるでしょう。
歳出総額を小さくする上で、規模が大きい社会保障への支出の見直しは必須となります。現在も年金・医療の分野を中心に見直しが議論されていますが、今後さらなる制度の変更が必要です。ですが少子高齢化が進む日本において、社会保障制度の見直しも強い反発が起こりやすい話題であると言えます。
上記の問題意識に基づいて、選挙など政治的なプロセスを通じて、政府債務発行が決まる仕組みをモデル分析した研究に取り組みました(Arai et al., 2018)。また、仮想将来世代を体験する経験により、今後取るべきと考える政策が変わる可能性があることを討議型実験で示しました(Nakagawa et al., 2019)。
3.今後、政府が取るべき財政運営の対策について
まずは、財政状況を改善するためにどのような取り組みが求められるかを整理し、政策提言を取りまとめることが必要です。そして提言をもとに、議会などの政治的なプロセスを進めて政策という形で実行しなければなりません。この課題には政治や行政も議論を進めています。経済学者などの研究者も分析や提言に取り組んでいます。
今後、より必要になる対策が2つあると考えられます。第一に、財政状況を改めるための取り組みに国民から幅広く理解を得ることです。第二に、支持してもらえる有権者やステークホルダーを増やす必要があります。これらの対策が必要な理由は、財政収支を改善する取り組みは、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があるからです。
税の支払いが増える、働き方が変わる、私たちが利用できる公共サービスが減ってしまう、などの悪影響が短期的にはあるかもしれません。このような財政運営を進めるには、国民からの理解と納得をどこまで得られるかが重要になります。
こうした点を進めるには有権者やステークホルダーが政策決定の場においてどんな意思決定や行動をとっているのか政治的なプロセスを通じて政策がどう決まるのかといったテーマに対する研究もさらに進めていく必要があります。
一見すると、後ろ向きな、暗い取り組みに見えるかもしれません。しかしこうした議論は、将来の日本や地域の姿を真剣に考える機会ととらえることもできるでしょう。将来どのような日本を目指すか、それにはどんな取り組みが必要か、を多くの人たちに考えてもらうべきです。
有権者やステークホルダーに議論に加わってもらうには、経済・財政に関する情報提供や、議論の場の形成が求められます。議論の場を形成するにはハード面の対策だけではありません。政治・経済の話題に対する心理的なハードルを引き下げるなど、ソフト面での対応も含まれます。多くの人たちが将来の日本を思い描き、社会がより良い方向に向かえば、明るい展望が見えてくる契機になるでしょう。
参考文献
Arai, R. (2011), “Productive Government Expenditure and Fiscal Sustainability,” FinanzArchiv (Public Finance Analysis),Vol. 67, No. 4, pp. 327-351.
Arai, R. and Ueda, J. (2013), “A Numerical Evaluation of the Sustainable Size of the Primary Deficit in Japan,” Journal of the Japanese and International Economies, Vol.30, pp. 59-75.
Arai, R. and Nakazawa, M. (2014), “A Numerical Analysis of Japan’s Fiscal Sustainability in a Simple OLG Model,” Applied Economics Letters, Vol.21, pp.1194-1197.
Arai, R., Naito, K., and Ono, T., (2018), “Intergenerational Policies, Public Debt, and Economic Growth: A Politico-economic analysis,” Journal of Public Economics, Vol. 166, pp.39-52.
Nakagawa Y., Arai R., Kotani K., Nagano, M., and Saijo, T. (2019), “An Intergenerational Retrospective Viewpoint Promotes Financially Sustainable Attitudes,” Futures 114, 102454.